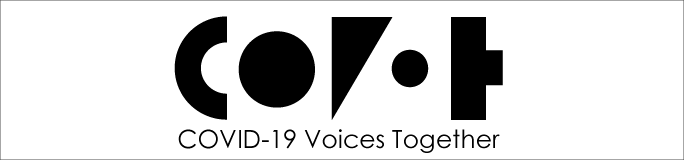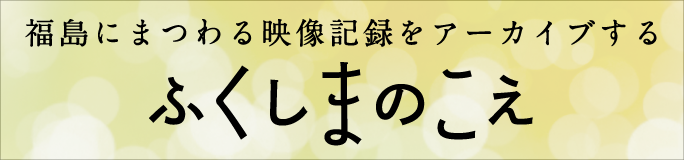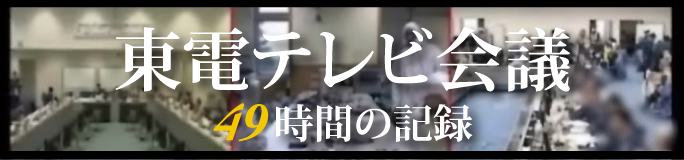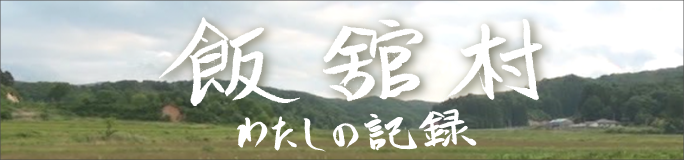マスコミが3月下旬、政府がパブリックコメント(意見募集)の「大量投稿」を問題視し、意見募集の方法や集約方法について再検討しているとの内容を報道した。これを受け、環境系のNPOやNGOが15日、合同で記者会見を行った。
会見を行ったのは、原子力市民委員会や気候ネットワークなど環境NGOなど14団体。司会を務めた国際環境NGOFoEジャパンの吉田明子さんは、日本では政策決定プロセスに、市民の参加の機会がなく、パブリックコメントのみに限られていると批判。また多数のパブリックコメントが寄せられたとしても、その意見はほとんど反映されず、形骸化してると指摘した上で、真の市民参加を実現することが大切であると述べた。
日本は「市民参加」の分野で立ち遅れている
環境国際NGO350.orgの伊予田昌慶さんは、「今回の動きはま国民意見ではなく、一部 産業会の声だけを聞いて政策を作りたいと いうま本音の現れ」と批判。「今年2月に決った温室効果ガスの削減目標は、市民の意見は全く反映されず、経団連が提案した数値と一緒だった。」とした上で、 昨年、水俣病患者の方と環境大臣の懇談会でマイクが強制的にオフをされた問題などと全て地続きだと指摘した。
またオーフスネット運営委員の中下裕子弁護士は、「国際的に日本は市民参加の分野で非常に立ち遅れている。日本の常識は世界の非常識世界の常識は日本の非常識」と批判。欧州では、「環境権」には、市民参加や情報アクセス、司法アクセスの3つが含まれるとするオーフス条約が締結され、世界の潮流になっていると指摘した上で、日本では「環境権」というと「実態的環境権」の議論に限られ、時代遅れの政策を続けていると批判した。
記者からは、行政が公聴会で業界関係者にやらせ質問をしている問題と、大量パブコメに差異はないのかといった質問が寄せられたほか、「除染土壌の再利用」について20万件以上のパブコメが寄せられたことについて、1面トップで批判的に報じた福島民友新聞の記者からは、パブコメの多くが、国際環境NGOFoEジャパンの文例をコピーしたものだったと指摘。認識を求める場面もあった。
「パブコメの抑制」考えていない
パブリックコメントを含む行政手続きを所管する総務省行政管理局調査法制課の担当者によると、パブリックコメントの問題が省庁で浮上したのは今年2月。事務次官の連絡会議で、大量にパブリックコメントが寄せられている問題が話題となり、総務省がいくつかの省庁にヒヤリングを実施。その結果、すでに3つの点について対策を行ったという。
一つ目は、パブコメを受け付けるオンライン上の行政受付サービス「e-Govと」に、「パブリック・コメントでは、提出された意見の「量」ではなく「内容」を考慮します。 同一内容の意見が多数提出された場合であっても、その数が考慮の対象となる制度ではありません。」との注意書きを掲載したという。2つ目は、1つのパブコメについて100件以上の意見が寄せられた場合、2週間の検討期間を設けるよう、従来から決まっている行政手続きを、あらためて各省庁に周知しなおした。さらに3つ目としては、「キリ番ゲット」など遊び半分で、パブコメを投稿する人がいることから、受付番号を連続で示さず、乱数で示すことにしたという。今後は、多数のパブコメに対応するため、AIなどを活用して意見の分類するなど、事務作業の効率化できるよう検討したいとしている。